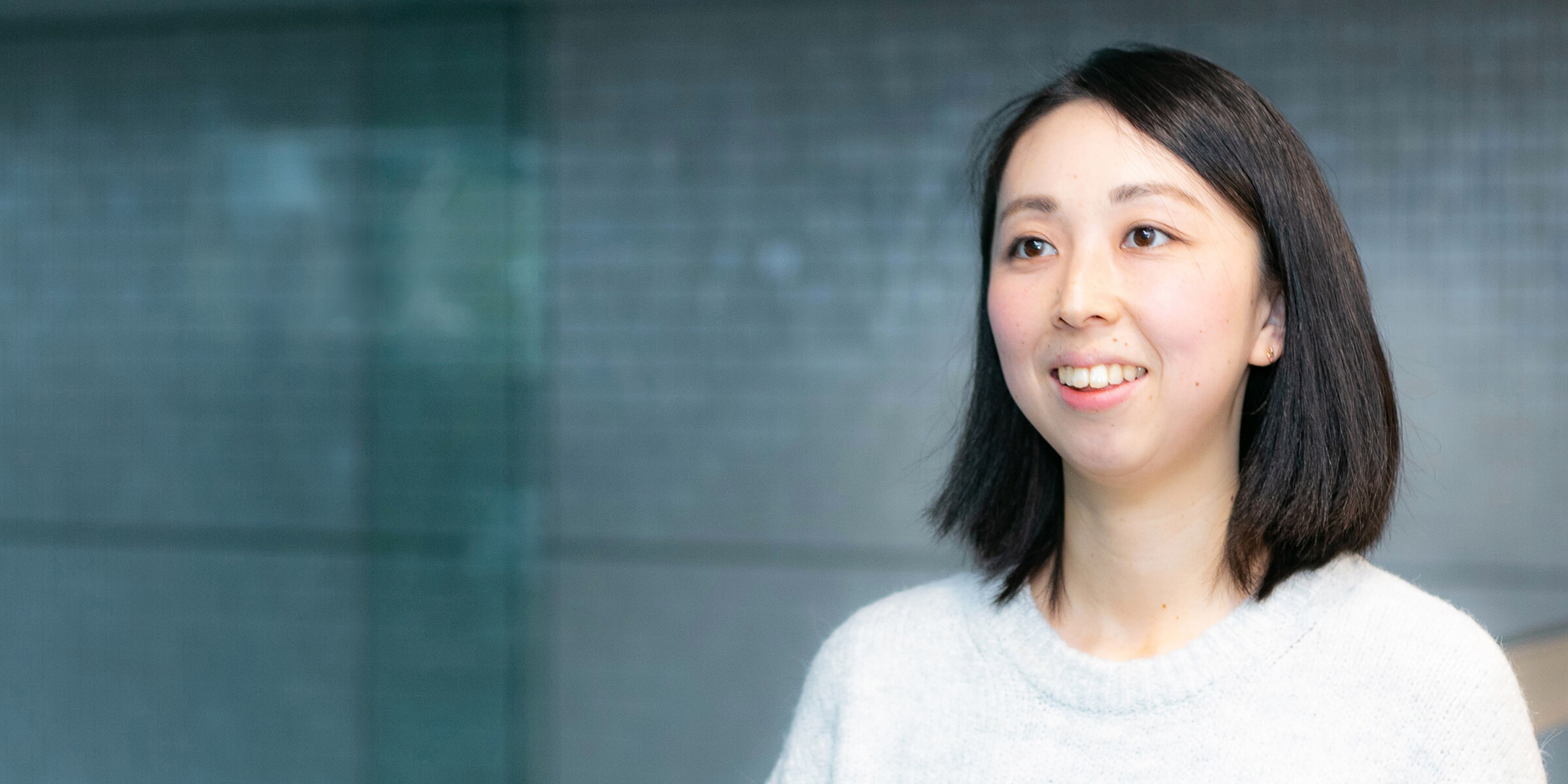DIVERSITY
DIVERSITY
ダイバーシティ
ダイバーシティ推進委員会
取締役および社員で構成するダイバーシティ推進委員会では、ダイバーシティへの様々な取組みについて議論がされています。働き方改革ならびにシニア世代および障がい者の雇用に関する議論などの内容で、働き方の多様性を実現する制度の設置や取組みに繋がったものもあります。
「男性の育児休業の取得」、「育児短時間勤務における子供の条件を小学6年生まで延長」については制度化され、「社員の事情によるシフト勤務の選択」、「テレワーク」などについては導入が進みました。
また、ダイバーシティ推進委員会の下部組織である女性部会では、女性社員のキャリア形成に向けた講演会や交流会を企画し開催しています。
ジャステックは、これからも多様な人たちが多様な働き方で幸せに働ける会社を目指し続けていきます。
女性活躍を推進する取組み
- ①採用環境
-
- 1980年代初頭より女性の採用を継続中(2024年11月末の女性社員比率:約25%)
- ②人材登用
-
- 能力のある女性を指導的地位(管理職、高度専門職)に登用
- ③活躍サポート制度
-
- 産前産後休暇(産前6週間、産後8週間の休暇の取得が可能)
- 育児休業(子が満3歳になるまで取得可能)
- 短時間勤務制度[妊産婦短時間勤務、育児短時間勤務(子が小学6年学年末まで取得可能)]
- 育児期間内の時間外労働および深夜業の免除(子が小学校3年生の学年末までを限度として免除)
- 育児シフト勤務(子が小学3年学年末まで取得可能)
- 育児看護休暇(子が中学校就学の始期に達するまで取得可能)
社員インタビュー
子供が生まれても、働き続けたいと思える会社
M.M /文系
2011年入社 SE(システムエンジニア)
就職活動では自分のつくったものが誰かの役に立つ仕事がしたいと考え、これからの生活に必要不可欠なものになるIT分野を志望。がんばり次第で男女の差がなく活躍できるジャステックの能力主義に魅力を感じ、結婚・出産を経ても復職して活躍している女性社員もいることから、ずっと働き続けられる会社だと思い入社を決める。現在は結婚し、子供が一人。2020年には二人目が生まれた。
結婚・出産から復職が当たり前という職場
私自身は結婚・出産を経ても、仕事を続けていきたいという考えを持っていますが、専業主婦になりたいという人がおられることにも理解をしているつもりです。
ライフスタイルが変化したときに、しっかりとした選択肢を持ち、選択可能な環境のあることが大切だと思っています。ジャステックは会社の制度や取組みが整っていることはもちろんのこと、一緒に働く上司や同僚たちが、妊娠中はいままで通りの働き方ができないことを見越してフォローいただいたり、産前産後休暇および育児休業の取得後は、復職することが当たり前といった意識で話をしてくれます。
私自身、妊娠中は妊産婦短時間勤務制度を利用して働いていましたが、体調に配慮していただいて産前休暇(産前6週間前から取得可能)より少し早く産前の二ヶ月前から休職することもできました。産前産後休暇および育児休業を合わせて一年半の休暇から復職した後にも、職場の上司から「自分にはわからないけど、大変さがあることは理解している」と言ってもらえ、気にかけていただいていることに大変有難く思いました。
復職後、子供が熱を出したりして出社できなかったり、早く帰る必要に迫られたときも、仕事をバックアップしてもらえるような体制があるのは大変助かります。もちろん、私も何かあったときに備えて、常に情報を引き継げるように整理しています。私の所属チームの男女比は6:4くらいで、ワーキングマザーのSEも5、6人います。3人のお子さんを育てながらバリバリ仕事をこなしている先輩SEもおられ、職場は女性としてのキャリアをイメージでき、相談しやすい環境だと思っています。

仕事への考え方を変えたら、家庭との両立が楽しくなった
私はもともと一人で仕事を抱え込むタイプでした。子供が生まれて短時間勤務に変わると残業をすることはできません。そのため、復帰して数ヶ月は仕事の進め方に試行錯誤していました。いままでと同じやり方では、時間が足りないのです。そんな私が仕事のスタイルを変えるきっかけになったのは、子供が一週間入院したことでした。そのとき、上司や同僚たちは、私が子供を最優先で考えられるように、仕事を引き継いでしっかりとフォローしてくれました。「無理なことは無理だと伝える」、「自分一人で抱え込まなくても大丈夫なんだ」と思えることができたのです。周りを頼るという心の余裕が生まれました。ゴールを明確にして、その日にやるべきタスクの優先順位を決め、退社時刻までに終わらなければ、見える化したタスクをしっかり引き継ぐのです。そういった考え方で仕事をするようになってからは、仕事と家庭をうまく切替えることができるようになりました。
子育てをしながら仕事を続けることの楽しさのひとつは、子供に外の世界を知ってもらえることですね。私が子供と一対一でずっと一緒にいることはないので、子供は自分を取巻く環境からいろんなことを吸収していくのですね。
一方、私は子供が保育園に通うようになり、働くママ友ができてからは、子育てだけではなく仕事の話もできるようになりました。子育てと仕事をうまく切替えながら、毎日を楽しめていると思いますね。

ワーキングマザーの先輩として、できることもある
私自身、ジャステックに入社してよかったと感じています。実際、こんなに長く働けるとは思ってもいませんでした。ダイバーシティやワーク・ライフ・バランスを支援する様々な制度が整備されていても、活用されていなければ意味がありません。その点、ジャステックはしっかり機能していて、私は仕事とプライベートをしっかり切替えながら働けています。出産後復帰してからは、仕事がより好きだと気づきました。いまはそんな風に思えています。
これからは後輩の女性社員が結婚したり、出産したりといった機会も増えてくるでしょう。そのときは、先輩として悩みを聞いたり、相談にのってあげられるような存在になりたいのです。私が入社したときに比べ、ここ数年でワーキングマザーの人数はすごく増えました。もっと人数が増えて、結婚や出産後も仕事を続けるという選択肢がいまよりもっと当たり前になるといいなと思っています。そのためには、自分の経験を伝えるとともに、私より年上のワーキングマザーと後輩との橋渡し役になっていきたいですね。